 書籍 「記憶の果て」
書籍 「記憶の果て」第10章 「詰め込む」のではなく 「引き出す」のが教育
1、150年前に消えたソクラテスメソッド
日本にもかつて寺子屋など学問を求める場所があった。古代アテネの人々は偉大な芸術を生み出した。
ソクラテスの時代から、対話や質問による学びあう教育があった。西洋の教育はこのソクラテスメソッドを基盤にしていた。
多くの生徒が教室に押し寄せ、ソクラテスメソッドは教壇から姿を消した。
教育はEducation(エデュケイション)といい”引き出すという意味”がある。だが現代の教育は、空のコップに知識をいれる詰め込みが行われている。
教育ではなく”指導”が行われている。
現代教育のゆがみや、偏りは非言語の音楽やダンス、書くことに重きをおかれなくなった。
その代償は生徒たちの知覚力を失わせ、学ぶ能力をなくしてしまった。
ではその退屈になる傾向のある学校形式の授業や会議はどうしたら対処できるのだろうか?
2.私にもしゃべらせて
人間には、自己表現の欲求がある。
もし私が会議に参加したとする。誰かが発言するときに、私は「こう思うのに」と頭の中で会話する。
その頭の中の会話とは「自分の発言には、どんなことを話ししようか」ということだ。
会議が進みずらいのは、このような人間の思考の原理による。
誰でも「意見を聞いてもらいたい」、それが自己表現の欲求だ。
会議が終わって、一番覚えていいるのが「自分の発言」だ。この自己表現の欲求はSNSやBLOGの広がりを見てもわかるだろう。
自己表現という欲求は、食欲や性欲と同じ本能だ。
この自己表現の原理を使った面白いノートの取り方がある。
講義や会議に応用できる方法が、フリーノーティングというものだ。
3.書籍に文字や絵を書き込む人たち
本に文字や絵を書き込むのがフリーノーティングの手法の一つ。
講義や会議にはメモを取りまくるのもいい。私も時々やっていた。
耳に入るキーワードを文字や絵にする。
自意識を忘れるくらい、集中して書きとめる。
これは自分の内側にあるデータを引き出す目的に利用する。
講義中は録音し、聞こえてくる刺激を自分の持っている情報と融合させる。
素早く書きとめ、その内容は講義や会議からそれてもいい。
これ会議でのストレスの軽減にもつながる。
つまり聞きながら自分の感じたこと、いいたいことを書きとめる>>自己表現の欲求をノートや本に書きとめることで、その原理を利用するわけだ。
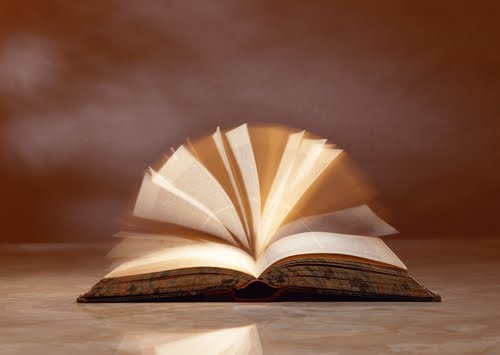

0 件のコメント:
コメントを投稿