 1.イメージストリーミングとうもの。
1.イメージストリーミングとうもの。学習の分野においてインプットは重要だが、それ以上にアウトプットが大切だ。
机に向って1時間学習したとする。じゃ何が分かった?
と質問すれば、結構理解したことが思い出される。
学習して「リマインド(思い出すこと)、もしくは何がいいたいんだろう?」と問いかければ、必要な答えがでてくる。
そもそも学習とは、どんな目的でやるのかが大切だ。
今回この書籍の中ので「隠された質問」とは、どんなことをやるのだろう?」という好奇心を持って読むことができた。
学習について好奇心や疑問点がわかると、「そういうことなのね」と納得でき、楽しい気分になる。
「頭脳の果て」という本は、かなりの内容の濃さだと思う。
この本のテーマ”イメージストリーミング”とは、自分の思い浮かんだことを声に出してメモをしたり、誰かに教えるように録音するというものだ。ちょっと変わった学習法かもしれない。
これは、自閉的もしくは自分の意見をきちんと説明できない人にとっては、福音ともいうべき内容かもしれない。
2.習慣というもの。
どんな人にも、コンプレックスはある。それを克服するために何かに挑戦する。でも続かない。
新しいことを習慣することは、難しいからだ。
では、何で新しいことが習慣とならないのか?
それは人間の脳は新しい情報にふたをするという傾向があるからだそうだ。
それを著者は”スカルチャ”と呼ぶ。
「音読がいいから続けよう、新しいスキルを身につけようと」と頑張ろうとすると、自分の声にふたをするものが現れる。
やったほうがいいと頭をかすめ、ほごにされる。そして、記憶から消し去られる。
それが「スカルチャ」だ。
脳は新しい情報が入ってきたり、意見や心から浮かび上がるものを、抑圧しようとするのだ。
これはメンタルブロックとも呼ばれる。
何かを暗記しようと試みる>>そうするとこのメンタルブロックが現れる。だから頭に入らない。
また環境によっても、抑圧される場合がある。
子供のころから「親からこうしなさい、ああしなさい」と言われ続けると、それに対して無視をしてしまう状態になるそうだ。
相手の話を聞いても情報を感知できず、知覚が鈍くなる。
本来脳の中では自由な発想やアイデアがわきあがっいる。それが感知できない。それを感知させるのはさまざまな知覚だ。
スカルチャは心の境界線ともいわれ、年齢を追うごとにその壁は厚くなる。
そういったスカルチャ、もしくは心の境界線を打ち破ってくれるトレーニングが「イメージストリーミング」というものだ。
3.音楽とモチベーション。
また学習を行う場合、脳は電池切れを起こすそうだ。そんな状態に充電してくれるのが、高周波の音楽なのだそうだ。
モーツアルトが、学習にいとされる理由もそんなところにある。
学習する際、深呼吸や目的達成のイメージを持つことなど、はじめに学習の準備が重要だと思う。
コリンローズ先生も、M.A.S.T.E.R.といわれる学習法で一番先にMind Set For Suceesをあげている。
クラッシック、ストレッチ、簡単な瞑想をすると、脳波を下げることができ学習に向かう準備を整えることができる。
学習はたのしい気分やわくわく感がなければ、無駄な時間を過ごす恐れもある。
自分に合った方法を探し、学習が加速していく>>まさにそれが加速学習というものだろうか?
いずれにしても好奇心や驚きが探究心や学習意欲をかきたてる。
既存の固定観念を説得するように、繰り返し何度も学習すればいいんだね。
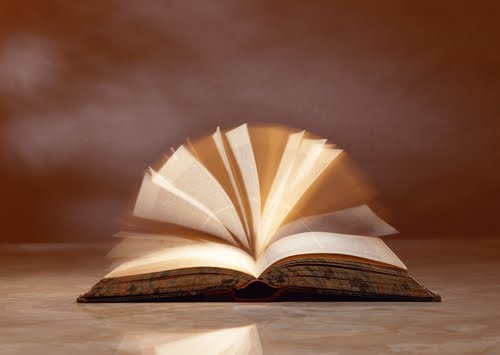

0 件のコメント:
コメントを投稿